コラム
02
子どもの「好き嫌い」には理由がある? 味わいたい気持ちを育てる、 幼児期からの味覚教育
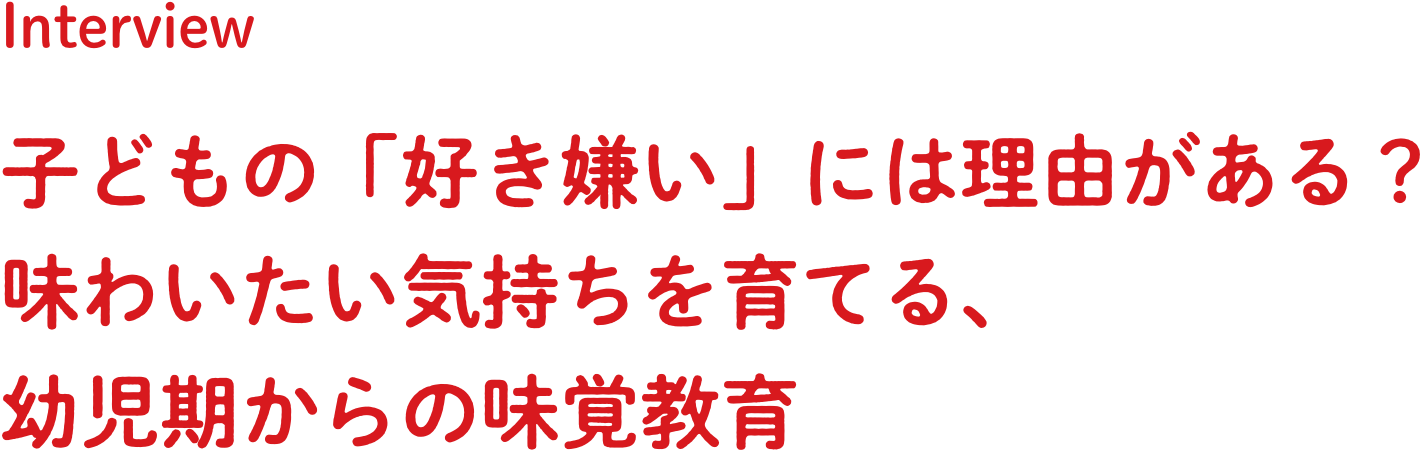

露久保 美夏 先生
東洋大学 食環境科学部 食環境科学科 准教授
専門分野は調理学、食育。主な研究テーマは食をサイエンスから紐解く調理科学と、全国の多様な食文化について。また、食育を通じて自己肯定感を高める「味覚教育」を中心に、親子向けの食育講座も行っている。
「野菜をまったく食べてくれない」
「給食の牛乳を必ず残してしまう」
子どもの「好き嫌い」が多く、このままでは偏食になってしまうんじゃないか。そうお悩みの親御さんも少なくないかもしれません。そもそも、得手・不得手を含む食の嗜好は、何歳頃からどのようにして形成されるのでしょうか? また、子どもの好き嫌いに対して、大人はどのように向き合えばいいのでしょうか?
「お子さんが苦手とする食材があったとしても、無理やり食べさせることはおすすめしません」と語るのは、東洋大学食環境科学部の露久保美夏先生(食環境科学科
准教授)。子どもの「味覚教育」にも取り組む露久保先生に、好き嫌いのメカニズムや、親としてできることなどを伺いました。
- 「味わう」をきっかけに、子どもの自己肯定感を高める
- 幼児期は「色んな食べ物を受け入れる準備期間」
- 買い物や料理に関わることで、食べ物との「心の距離」が縮まる
1. 「味わう」をきっかけに、子どもの自己肯定感を育む
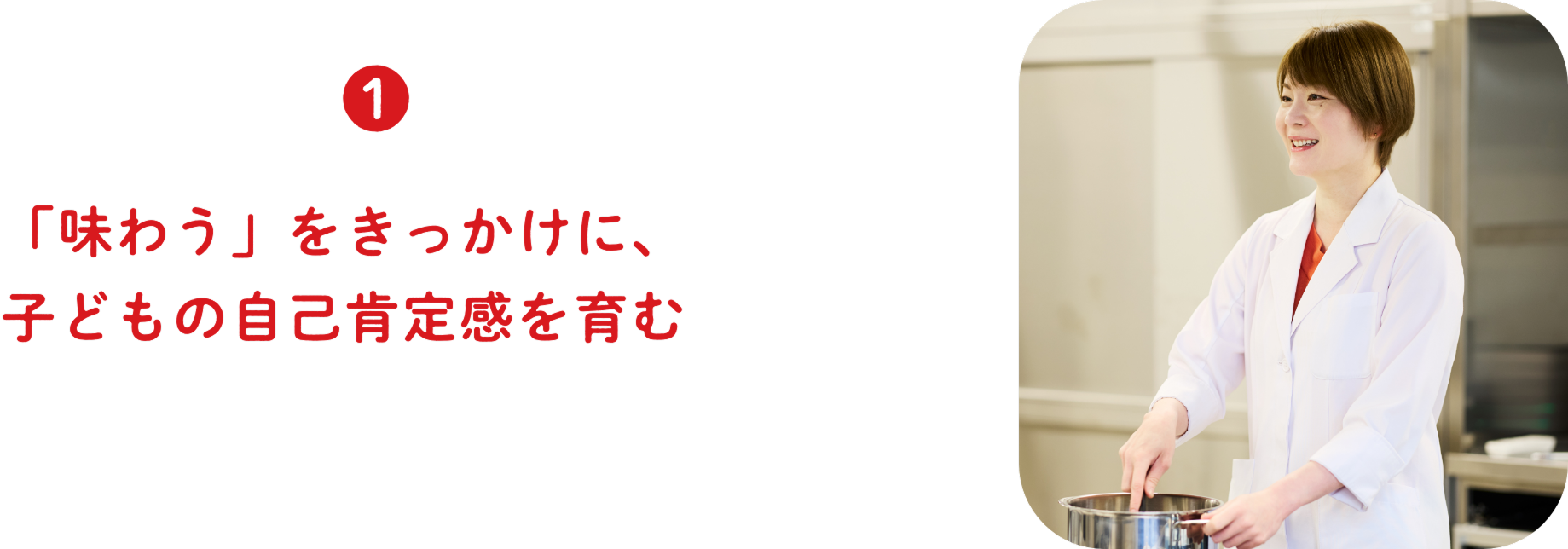
- —— 露久保先生は幼児や小学生の子どもたちを対象に、「味覚教育」の講座を開催しています。その目的や講座の内容を教えてください。
- 味覚教育というと、舌の感覚を養うとか上手に食べられるようになるための教育といった印象を抱かれがちですが、そうではありません。目的のひとつは、食べることを通じて幼い頃から「自身が生きやすくなる気持ちのあり方」を知ること。それにより豊かな人間性を育んでいくことです。
- —— 「食」と「生きやすくなる気持ちのあり方」が、どのようにつながるのでしょうか?
- 私たちが取り組んでいるのは、食べ物の味わいを通じて「自分は自分でいいんだ」という自己肯定感が芽生えていくようなアプローチです。たとえば、子ども同士のグループで何かを食べて感想を言い合う場があったとします。そこで自分の感じ方が他のみんなの感想と異なっていた時に、言葉を引っ込めてしまう子って結構いるんです。自分は苦手な味だなと思っても、みんながおいしそうに食べていたらなかなか言えないですよね。でも、感じ方は人それぞれなのだから、本当は素直に意見を言っていいと思います。
- —— 他の子のおいしいという感想を否定するのではなく、あくまで「自分はこう感じた」ということですよね。
-
はい。そして、味覚教育では子どもたちに、「なぜそう感じたのか?」を考えて言語化してもらいます。苦手なのは味なのか、においなのか。もしかしたら見た目や感触、温度なのかもしれない。ネガティブに感じたことにも向き合って分析し、それをみんなで伝え合う。そうすることで、自分の思いや感じたことをしっかりと表現できるようになっていきます。
自己認識や自己肯定感を育むトレーニングとして、食はとてもいいきっかけになります。また、人とは違う感じ方を自分自身が認めてあげることで、他者の感じ方も否定せずに受け止められるようになる。味覚教育を通じて、そんなマインドを持った人が増えてほしいという思いもあります。 - —— ただ、自分の感覚を表現することが難しい子もいると思います。味覚教育では、どのように言語化をしてもらうのでしょうか?
-
大事なのは対話です。たとえば、子どもが「おいしくない」と言ったら、その言葉の背景を対話によって丁寧に汲み取っていきます。本人の感じたままを引き出す必要があるため、誘導するような問いかけはしません。また、「え〜?」「そんなことないでしょ?」といった、過剰で否定的なリアクションをしないことも重要です。大人にとっては何気ない一言でも、子どもは「自分の感じ方は間違っているのかな」「おいしくないって、言っちゃいけなかったのかな」といった具合に、気持ちが萎縮してしまうからです。
決して否定せず、「そうなんだ。じゃあ、どうしてそう感じたの?」と、淡々と聞いていきます。「そう感じたのは間違いじゃないんだよ」「ここは“正解”を求めている場ではないんだよ」という雰囲気をつくりながら対話を重ねると、最初は発言をとまどっていた子どもたちも徐々に自ら言葉を紡いでくれるようになるんです。 - —— そうなると大人も辛抱強く、子どもと向き合う必要がありますね。
- 子どもからなかなか言葉が出てこないと、大人はつい「こうだよね?」とサポートしたくなってしまいますよね。でも、ゆっくり味わって、ゆっくり言語化する子もいます。黙っているように見えても、本人はすごく考えているんです。ですから、口に入れた瞬間に質問するのではなく、まずは「味わう時間」をつくってあげる。そのうえで、「どう感じた?」というオープンな聞き方をして、たくさんの言葉を引き出すことが重要です。そうすれば、子どもたちもちゃんと食べ物の味わいや個性をキャッチし、頭の中で言語化して表現することができるようになると思います。
2. 幼児期は「いろいろな食べ物を受け入れる準備期間」

- —— 子どもの頃は苦手だった食べ物を大人になってから好きになるなど、同じ人でも年齢によって味の感じ方が変化することがあります。特別なきっかけがなくてもこうした変化が起こる理由を教えてください。
-
味覚の形成にはそれまでに重ねてきた「食経験」が大きく影響します。子どもの頃は口にした経験が少なく苦手だと感じていた味も、慣れによって自然と食べられるようになることは少なくありません。たとえば、人間には生まれつき「苦味(毒を含んでいるかもしれない)」「酸味(腐っているかもしれない)」を回避する本能があり、幼いうちはほとんどの子が苦手としています。ただ、苦いものや酸っぱいものを食べ重ねることにより、少しずつ慣れていくわけです。
また、それを食べた時の楽しい記憶と結びつくことで、好きになるケースもあります。たとえば、最初はピーマンの苦味をおいしくないと感じていても、みんなで食事して楽しい気分になった! 調理の仕方でちょっと食べられた! などの経験を積み重ねるにつれて、徐々にピーマン自体を好きになっていくことも考えられるでしょう。 - —— 味覚というのは人間の本能や心理とも強く結びついているし、それだけ変化しやすいということですね。ちなみに、子どもの「好き・嫌い」は何歳頃から形成されるのでしょうか?
- 子どもによって食経験が異なるため、明確に何歳という線引きは難しいです。ただ、一般的には3歳くらいになると、ちゃんと食べ物の個性を認識したうえで、自分から「嫌だ」という意思表示を行うようになるといわれていますね。また、10歳くらいまでにある程度の食べ物を経験すると、そのうえで「甘いものが好き」「酸っぱいものが苦手」など、おおよその好き嫌いが固まってくる傾向はあります。
- —— 小学校に上がる前の段階で、いわゆる「好き嫌いが多い子」もいます。克服してほしいと考える親御さんも多いと思いますが、どうしても食べてくれない場合の対応策などはありますか?
-
対応策の前に、まずは子どもの食経験が不十分なタイミングで、食べないことに対して怒ったり、無理やり食べさせたりするのは避けてほしいと思います。繰り返しになりますが、その時には嫌がっても徐々に食べられるようになることも少なくありません。また、なかには未知のものに対して恐怖心を抱き、距離を置きたがる子もいます。子どもがまだ幼いうちは、親御さんが「今はいろいろな食べ物を受け入れる準備期間」と捉えてあげる姿勢を持つことが大事です。
それがまず前提で、対応策としてはやはり対話ですね。対話を通じて食べなかった理由を探ることで、解決方法が見えてくるかもしれません。味ではなく見た目やにおいが苦手なら、調理方法を変えることであっけらかんと食べてくれることもあるでしょう。また、子どもによっては感覚過敏で、たとえばエビフライを食べるときに「口の中がチクチクして痛い」と感じるケースもありました。食材そのものではなく調理法に「苦手」の原因があることも想定されます。大人はいろいろな可能性を考慮した上で、その子の食べ方や反応を丁寧に見てあげてほしいですね。 - —— 逆に、子どもへのアプローチとして好ましくないことはあるでしょうか?
-
避けてほしいのは、「強要」と「比較」です。今は少なくなっていますが、小学校などで給食を食べきらないと昼休みに入れないといったことがありませんでしたか?
みんなは遊んでいるのに、自分は教室の端っこで泣きながら食べている。そんな罰ゲームのような苦痛を与えられると、その食べ物だけでなく食事そのものが嫌いになってしまうことだって考えられます。
比較については、家庭でも兄弟間などで起こり得るケースがあります。たとえば、苦手なものをなかなか食べられない弟の前で、「お兄ちゃんは食べられて偉いね」と、兄を褒めたりすることが当てはまります。大人にとっては何気ない一言かもしれませんが、それを聞いた弟は大きなストレスやショックを受けてしまうかもしれません。 - —— 「体にいいんだから残さないで食べなさい!」も「お兄ちゃんは食べてるでしょ」も、つい言ってしまいがちな気がします。
- 険しい顔でそう言われるより、大人が「おいしい、おいしい」と笑顔でもりもり食べている姿を子どもに見せてあげるほうがいいと思います。身近にいる人の模倣は子どもの学びや成長につながりますし、食卓をいかに安心できる空間、食事を楽しめる空間にできるかは、やはり大人の影響が大きいですから。
3. 買い物や料理に関わることで、食べ物との「心の距離」が縮まる
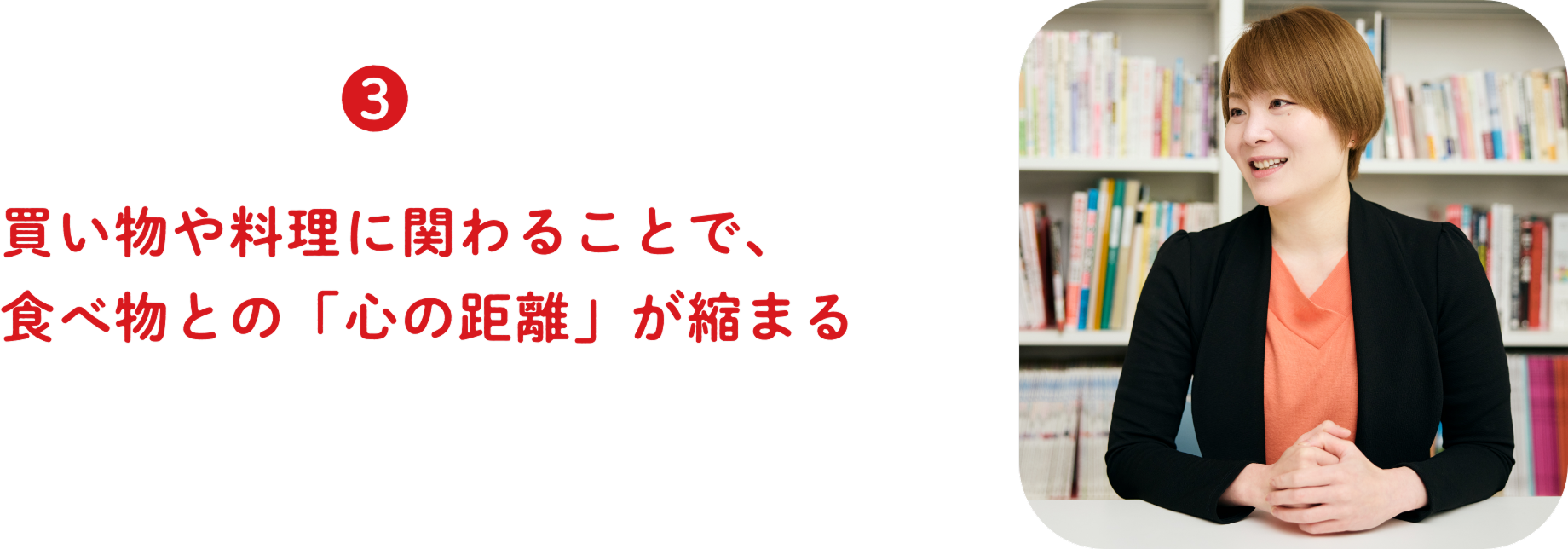
- —— 露久保先生の講座には牛乳が苦手という子もいるかと思います。どんな理由が多いのでしょうか?
- 私が聞き取りをした限りでは、においが苦手という子がいました。また、牛乳自体は嫌いじゃないけど、温度によって味の感じ方が変わってしまって、ぬるいと飲めないという話も聞いたことがあります。
- —— 普段あまり牛乳を飲まない子に、強要することなくおいしさを感じてもらうために、おすすめの方法はありますか?
-
牛乳もメーカーによって殺菌などの製法が異なり、一つひとつ味が違いますよね。大学で私が受け持つ調理の授業では、学生に3種類の牛乳をブラインド状態で飲んでもらい、それぞれの味の違いを言語化する官能評価を行うのですが、そこで牛乳の新たな魅力を発見する学生もいます。それまでは牛乳ってどれも同じだと思っていたけど、意識して味わうと違いに気づき、初めて自分が好きだと思える牛乳に出合えたという声も聞かれました。ですから、今あまり牛乳を飲まなかったとしても、それはまだ自分が好みの味を発見できていないだけなのかもしれません。少なくとも現段階で、「この子は牛乳が嫌い」と決めつけることはないと思います。
また、牛乳に限らず食べ物全般に言えることですが、食べ物との「心の距離」を縮めるということも、とても大事です。 - —— 心の距離、というと?
-
先ほども少し触れましたが、幼い子どもにとって誰が作ったか分からず、あまり口にしたこともない食べ物って、恐怖心を伴うこともあります。それは、いわば食べ物との心の距離が遠い状態であるともいえます。親御さんや大人が少しサポートすることで、これを縮めてあげることはできると思います。
たとえば、小学生たちと一緒に乳製品を使ったアイスを手作りしたことがありました。できあがったアイスをパクパクと食べていた子の親御さんが驚いて「この子は乳製品全般が苦手で、普段は全く食べないんですよ」とおっしゃっていたんです。それもおそらく、自分がつくったことで牛乳との心の距離感が縮まった結果ではないでしょうか。 - —— 家庭でも、料理の際に包丁や火を使わない工程を子どもにお願いしてみるなど、できることはありそうですね。
-
スーパーで買い物をする際に、どの牛乳がいいか、どの食材がおいしそうか、子どもに選んでもらうだけでもいいと思います。大事なのは、少しでも自分がそこに関わるという体験。そうした体験を積み重ねるうちに、食材や食事への向き合い方が変わってくるはずです。その結果、敬遠していたものも積極的に食べてみたい、味わいたいという前向きな気持ちが形成されていくのだと思います。
食べ物を「おいしい」と感じるのは味覚だけでなく、楽しい雰囲気や思い出も関係しています。子どもには、嫌いなものを無理に食べさせるのではなく、「いつか好きになれたら」と温かく見守ることが大切です。子どもとの対話を通して、親子で一緒に「好き」を増やしていける環境を作っていけるといいですね。